漱石 親に愛されなかった子

根岸の競馬場が完成したころ。
夏目金之助は生後間もなく里子に出されている。理由はよくわからない。
苗字も夏目姓から養家の塩原姓に代わっている(実際に変わったのは5歳、明治5(1872)年)。幕末から維新にかけての激動の中で、「できるだけ扶養家族をへらしたいような父親の心境」があったのではと、文芸評論家の江藤淳は書いている。
後年の漱石は書いている―
「私は両親の晩年になって出来た所謂末ッ子である。私を生んだ時、母はこんな年歯をして懐妊するのは面目ないと云つたとかいふ話が、今でも折々は繰り返されてゐる」
この言葉を「衝撃的な告白」と評するのは、同じく評論家の三浦雅士である。
この告白は、死の前年(大正5(1916)年)、48歳ごろに書かれた小品『硝子戸の中』に登場する。これが小説『道草』につながっていくとされるのは、漱石ファンなら周知の事実であろう。
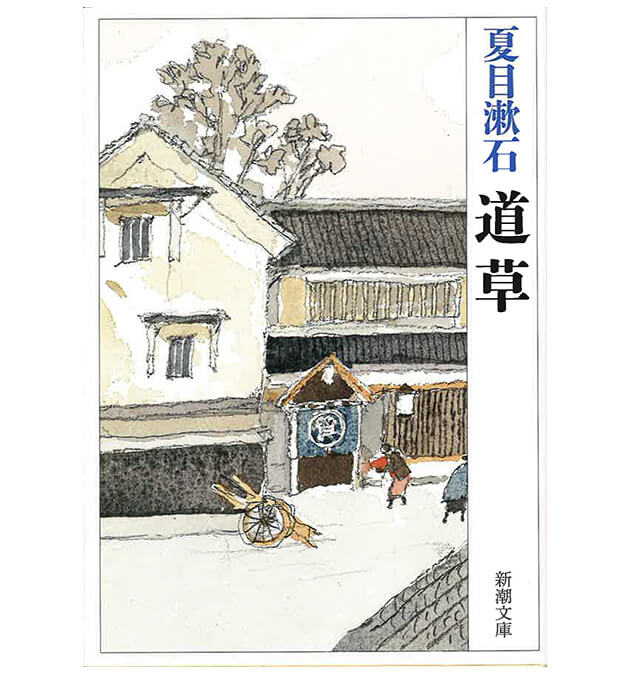
夏目漱石『道草』新潮文庫
"私小説"とも言われるこの小説では、主人公の健三(漱石と目される)と養父・島田(漱石の養父だった塩原昌之助と目されている)らとの間で、たとえば、こんな会話が展開されている。
(『道草』四十一より)
《彼等が長火鉢の前で差向いに坐り合う夜寒の宵などには、健三によくこんな質問を掛けた。
「御前の御父ッさんは誰だい」
健三は島田の方を向いて彼を指した。
「じゃ御前の御母さんは」
健三はまた御常の顔を見て彼女を指さした。
これで自分達の要求を一応満足させると、今度は同じような事を外の形で訊いた。
「じゃ御前の本当の御父さんと御母さんは」》
これは実話なのだろうか。小説の中の"健三"は
「いやいやながら同じ答えを繰り返すより外に仕方がなかった」
と辛い心情を吐露している。実際の金之助少年の場合は、その後、養父が外に女を作ったことで、養母と一緒に家を出るが、養夫婦が正式に離婚したため養父に引き取られる…。
この辺りについて、前掲したふたりの漱石研究家の言説を紹介しておこう―。
「とにかく十代のはじめまでは(漱石は)家庭崩壊の現場をうろついていたようなものなのです」(三浦雅士)
「(「じゃ御前の本当の御父さんと御母さんは」)この問は必然的に金之助をある根源的な問に直面させてしまう。自分はいったい誰に、どこに属しているのだろう? それは彼の内部の闇に反響し、意識の奥底に喰い入り、やがて鉛のように存在の深層に沈澱する」(江藤淳)
この間、東京は明治元(1868)年の"御維新"を経て、急速に変貌していく。約700か所に及ぶ町名変更が強行され、「神仏分離」の新政策が採られ、上野では不忍池を埋め立てて桑茶園にしようとする計画まで持ち上がっていた。急激なインフレは収まるところを知らず、かつての武家屋敷は軒並み競売に出されたが、まったく買い手が付かなかった…。
© Net Dreamers Co., Ltd.
